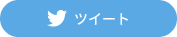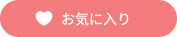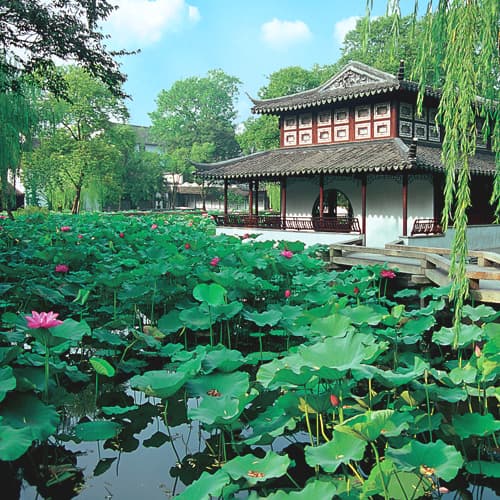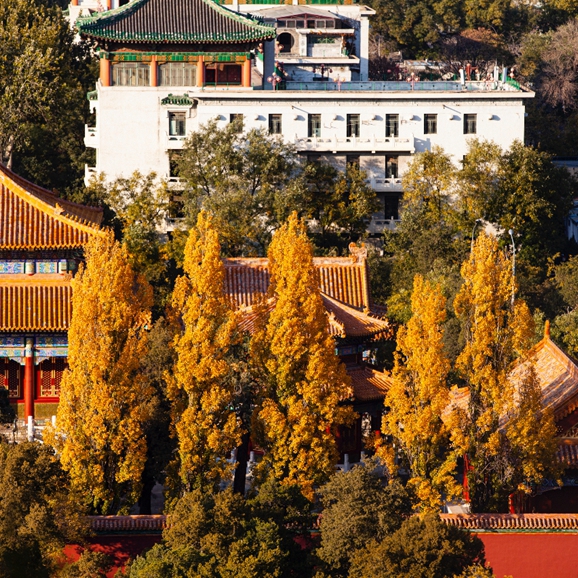中国全土を見渡しても、沙県のように街角の小吃で全国チェーンを築き上げた場所はほとんどない。山々に抱かれ、沙渓河が街を横切る——沙県はまるで小吃の碗の縁に支えられた盆地のようだ。一見ありふれた小吃だが、その味には中原と南方の食文化が交わり、移ろってきた歴史が刻まれている。晋の末、唐の末に二度の南渡がもたらしたのは、小麦の香り、麺の文化、葱やにんにくの風味、そして蒸す・煮る・焼く・揚げるといった技法。それに地元の閩南の淡麗な味わい、客家の塩気と辛味、さらには閩越・畲族の山海の食材が溶け合い、今日の“沙県の味”が生まれたのだ。


映画『廊橋を出て』の中で、アータオが祖伝のワンタンを抱えて小さな町を飛び出す姿——それはまさに現実の写し絵だ。1992年、標会(民間の互助金融組織)が崩壊した後、借金を背負った沙県の人々は鍋や茶碗を背負い、全国へと散っていった。ビニールシート一枚、石炭コンロ二つ、そしてワンタン鍋一つ——「1元で入って、2元で満腹、5元で満足」という理念が、数え切れない人々の“致富の夢”を支えた。親戚や同郷との“ネットワーク”に支えられ、「つながるが縛られない」家内工房の仕組みが、世代を超えて彼らを生き抜く道へと導いていった。


経済の回復とともに、沙県小吃は“生き残り”から“拡大”へと舵を切った。北上して上海や北京に進出し、協会を設立し、ブランド化を進め、セントラルキッチンを整備——夫婦で営む個人店は、次第に体系的な経営モデルへと置き換えられていった。味もまた市場によって“選別”され、複雑すぎる料理やあまりに地方色の濃い品は姿を消し、残ったのは、シンプルで早く、どこか家庭の温もりを感じさせる“スター料理”。無数の都市で働く人々や学生たちの胃袋を満たしている。
しかし、郷土誌をめくれば、地元の小吃はいまも数多く息づいている。佳蘭焼売、羅蘭焼餅、廟門扁肉、李記小吃……それらはチェーン店の波に乗ることはなかったが、故郷の味を守り続けている。本当にうまい味は、いつだって目立たない小さな店構えに潜んでいる。通りに面した竈台、立ちのぼる湯気、木の卓とプラスチックの椅子——そこに集う地元の人々こそが、この町いちばんの“看板”なのだ。


沙県の人々は自分たちの技を隠さないが、その工程は決して簡単ではない。地元の食卓で主役を張るのは、実は蒸し餃子ではなく芋餃(ユージャオ)だ。里芋のペーストに蕨粉、干し筍、豚の赤身を混ぜて三角形に整え、金銀の延べ棒のように透き通る。
スープを添えたいなら、ぜひ豆腐湯を試してほしい。前日の豆乳を発酵させた「老漿水」で寄せ固めた豆腐は、きめ細かくなめらか。“烫嘴豆腐(タンジュイトウフ)”は干し金針菜とアサリの干物とともに煮込まれ、澄んだ味わいと深い旨みが広がる——それは多くの人にとって、故郷を思い出させる味なのだ。


沙県の小吃はいかにして世界へ広がったのか?それは――「一つの鍋と二人」から始まり、三十年以上をかけて全国区の名を得た、その道のりにこそ答えがあるのかもしれない。決して速くはなかったが、一歩一歩、着実に進み、家庭の味を人々の記憶に刻み込んできた。めまぐるしく変わる都市の中で、人は本能的に“変わらないもの”を求める。沙県小吃とは、まさにその“安らぎと恒常”の象徴なのだ。